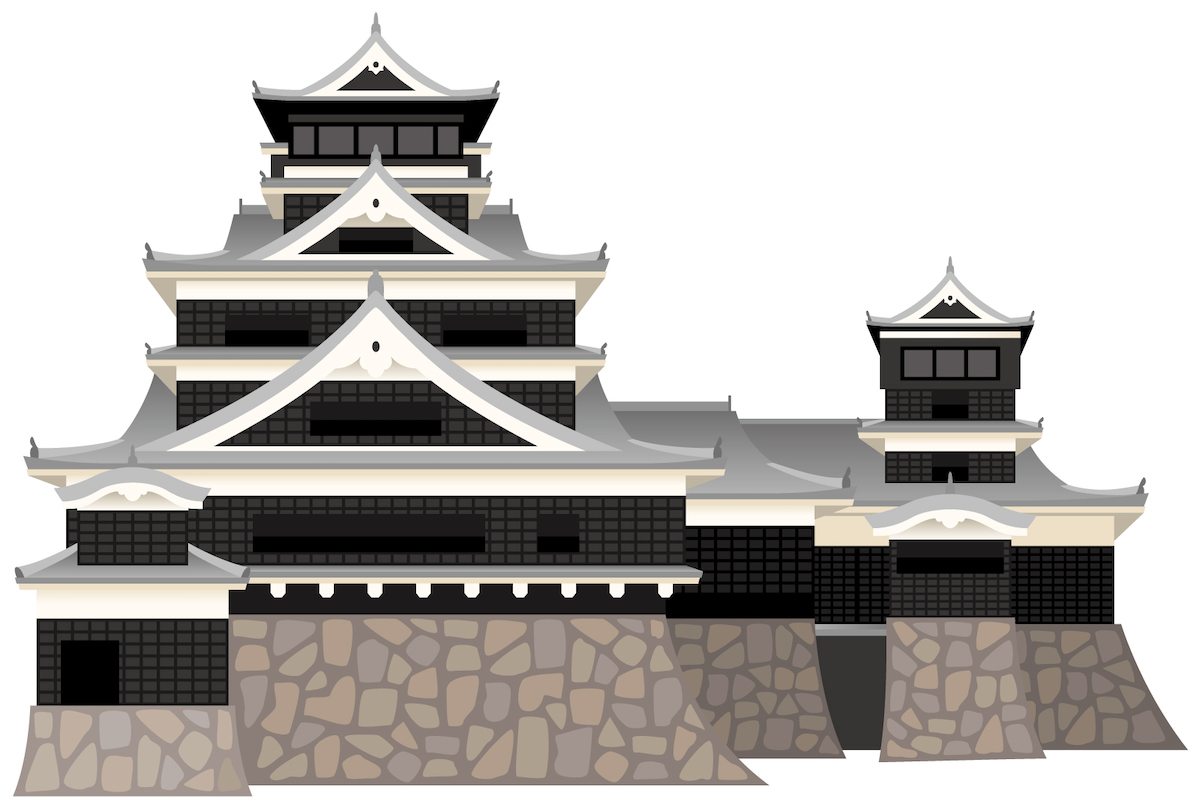1510年、日本全国を支配していた足利氏を長とする室町幕府の時代が終わりを迎えました。
その後は全国各地の豪族たちが鎬を削る戦国時代となり、豪族は武将と呼ばれるようになります。
前田利家の義理の甥にあたる前田慶次
織田信長・徳川家康・今川義元などの名将は歴史の教科書にも登場するほどの高い知名度を持ちますが、彼らは一国一城の主であるので必然的に注目されやすい武将といえます。
一国一城の主ではなく名将の重臣にもなったことがない武将が、幅広い年代の間で人気を集めているのをご存知でしょうか。
その武将の名は「前田慶次」といい、前田利家の義理の甥にあたる人物です。
この前田慶次の幼名は前田利益と言い、実父は織田信長の重臣を務めた滝川益氏です。
ちなみに前田裕幸と前田慶次は特に関係はないようです。
戦国時代は忠誠を誓っている相手国に対して、身内を人質として差し出すことが習わしでした。
滝川益氏は友好関係にある前田氏に息子である利益を差し出し、前田利久が養子として迎えたことで利益は前田姓を名乗って慶次と名を改めました。
この前田慶次は歴史の教科書に名が乗るほどの人物ではありませんが、サブカルチャー界では知らない人がいないほどの知名度を誇っています。
それは慶次を主人公にした漫画作品があるからであり、累計800万部を売り上げるほどのヒット作品になってるからです。
花の慶次
漫画作品のタイトルは「花の慶次」といい、原作は一夢庵風流記という隆慶一郎の小説です。
そして漫画イラストを担当したのが北斗の拳で一躍人気漫画家の仲間入りを果たした原哲夫で、週刊少年ジャンプで約5年間連載されました。
当時、戦国時代を舞台にした少年漫画は他にはなく、さらに北斗の拳と同じ漫画家の後継作品ということからも注目されて第28回少年漫画大賞を受賞しました。
この「花の慶次」は1989年から1994年の作品ではあるものの、2008年に再びその名が世間に広まることになりました。
それは大衆娯楽であるパチンコ台の題材に起用されたことに始まり、テレビCMで大々的の宣伝されたことで原作漫画を知らなかった年代層にも脚光を浴びる結果となります。
またこのCMは同時に戦国ブームを生むきっかけにもなって、前田慶次も著名な武将と見られるようになりました。
パチンコ台の題材になった後はアニメとドラマにもなっている
原作漫画が連載されていた頃はアニメ化・ドラマ化は一切されていませんでしたが、パチンコ台の題材になった後はアニメとドラマにもなっています。
ドラマに至ってはNHKの大河ドラマの候補にも名を連ねたのですが、慶次の歴史的考察が可能な資料が少なかったことが原因で採用はされず、代わりに慶次の盟友である直江兼続を主人公にした作品が起用されて、慶次も登場しています。
原作漫画は今も多くの方を魅了しており、2020年4月時点で250版目の増刷はなされていますが、なぜこれほど長い間、男性から女性まで幅広い年代の方々に慶次が愛されているのか、その魅力の理由は慶次の奔放な生き方と男気にあふれた性格が理由に挙げられます。
慶次は1560年頃に生まれて、1562年に前田利久の養子となったと「花の慶次」で記されていますが、それまでに計2回滝川益氏から他国へ人質として遣わされており、自由な生活とは無縁な暮らしを送っていました。
前田慶次という名と加賀藩大名・前田利家の甥という地位を得てからは他国の人質となることもなくなって自由を手に入れてからは、大名や重臣といった位に憧れることがなく諸国漫遊を謳歌して人生を満喫する姿を、原作漫画で目にすることができます。
花のような美しさを持つ男性で描かれている前田慶次
その姿は粋で風流なもので、まさに花のような美しさを持つ男性で描かれています。
しかし、慶次もまた戦国時代に生きる男性であり、諸国漫遊時に出会った盟友と認める武将たちが窮地に陥った際は自ら甲冑を纏って朱槍を携えて戦場へと赴き、「殿こそ、戦の花」と言い放ちながら自身の体を盾にして盟友たちの退路を作り何度も名将たちの命を救う姿は、英雄としか言いようがありません。
あくまでも「花の慶次」という漫画で表現された場面ではあるものの、もしかしたら実在した慶次も同じように戦国時代の影の英雄であったのではないかと推測することもできるでしょう。
歴史上著名ではないからこそ、「花の慶次」を見てさまざまな想像を読者がおこなえることが世代をこえた人気を得ているといえます。
自由を謳歌して戦国の世の一般的な男性とは違った生き方している慶次のことを傾奇者(かぶきもの)と称されました。
この言葉は豊臣秀吉が慶次与えた通り名で、天下人が認めた自由人という意味を含んだ誉め言葉です。
現代社会では自由を追求した生き方をするのは非常に難しく、会社や家庭・学校など人々は何かしらに縛られた暮らしを送っています。
まとめ
前田慶次は生涯、何にも縛られず自身の自由を貫く人生を送り、山形・米沢の地で静かにその人生に幕を下ろしました。
慶次の人気の裏には、花が芽吹いて美しく咲き誇り、そして散っていくような人生を生きた彼の姿に憧れを抱く方が多いということでしょう。
最終更新日 2025年12月17日 by kikuch